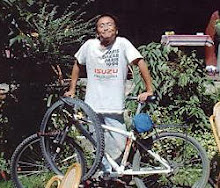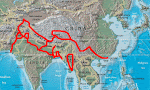インドネシア地震で発生した津波はインド東海岸に甚大な被害を及ぼし、多数の死者・行方不明者を出した。
バラナシは内陸なのでもちろん何の影響もなかったが、テレビでは連日このニュースばかり。
で、ここで私はふと思うのだが、このような深刻な災害を、政府やその関係者はむしろ歓迎しているのではないだろうか?
というのは、こういう時に真っ先に亡くなるのは税金も納められない最下層の人たちであって、国にとっては存在価値はなく、逆に人口が減って食糧問題解決になる、と喜んでいるのでは?
更に嬉しいのは海外から大量に送られてくる援助物資を横流ししてガッポリ儲けられる絶好のチャンスであること。
事実、しょっちゅう洪水に遭うお隣の「被」援助大国バングラデシュには横流しマーケットなるものが公然と存在する。
そこに集まる古着の中にはビンテージジーンズのような掘り出し物が時々見つかるとかでマニアが買い付けに来るらしい。
と言うわけで今頃インドの高官たちは笑いが止まらぬのではないかと思うのだ。
余談であるが、「津波」のことを英語で「Tsunami」と言うことを今回初めて知った。
2005年1月2日日曜日
火事・オヤジ
明けましておめでとうございます
謹賀新年。
2年前と同じくインドのバラナシでの年越しとなりました。
といってもヒンズー教の総本山的なこの街では「正月」の「し」の字もない(「クリスマス」の「ク」の字もなかった)、ただカレンダーを2005年のに取り替える程度の日でしかありませんでした。
アジア諸国で新暦の1月1日にお正月を祝うのは日本とあとどっか一国(フィリピン辺りか?)しかない、と聞いたことがあります。
その他は旧正月や、イスラム暦・ヒンズー暦・チベット暦などの宗教正月に盛大にお祝いします。
我々が何の疑いも持たず正月を祝っていることは、実はアジアの中では「西洋かぶれした例外的な国」だった訳ですね。
まあそれはともかくとして、本年もどうぞよろしくお願いします。
2004年12月16日木曜日
ありがたや、ありがたや
バラナシに2年ぶりにやって来て「今までどこで何してたんだ?」と聞かれたので
「本当はもっと早くインドに来るつもりだったのだがインド大使館がビザをくれないのでパキスタンとかチベットへ行って時間稼ぎしてたんだ。
ついでにカイラス山にも行ったよ。」と答えた。
すると急にみんなの顔付きが変わり
「何!カイラスに行った?! おーい、みんな集まれ!!!」
と、一家総出(20人くらい)で次々と私の前に膝まづき、水虫はないけど時々ウンコを踏んだりするとてもきれいとは言い難い足に触れ、ありがたがるではないか。
ヒンズー教徒にとっても、カイラス山はガンジス川の源として(本当は違うが)最大の聖地の一つであり、山の形をシヴァリンガ(男性のチンポコ)に見立て(かなり無理がある)崇め奉っている、ということは知っていたがここまで有り難がられるとは思ってもみなかった。
翌日には話を聞いた近所のジイさんとかもやって来て
「どれワシも冥土の土産に一触りさせてもらおうかの」
みたいな感じでペタペタ。
そこでピンと閃いた。
これはゼニになる!
1回1ルピー(2.5円)で触らせても、ヒンズー教徒人口は8億人くらいいるので20億円!!
こりゃ帰国は自家用ジェットだな。
ただし1人10秒ずつで1日4000人さばいたとしても、550年かかるが。
(写真:聖地チンポコ山)
2004年12月7日火曜日
食事の話
私はどんなものでもおいしく食べられてしまうくちなので旅先でも困ることが少ない。
ツァンパはまずい、と書いたけどあれはネタ上のことであって本当はおいしく食べている。
腐っているもの食べても、この料理はこういう変な味付けなんだな、ウマイ!と食べてしまって翌日腹壊す。
だから「この辺でウマイ店知ってますか?」と聞かれると大変に困ってしまう。
どこだって美味しく思えるからだ。
ただ、たった一つだけどうしても食べられないものがある。
それは「レバー」。
これはもうウマイ・マズイの話じゃなくて人間がプラスチックを食べられないように、私にはレバーは食べられないのだ。
で、ある時チベットで。
明らかに貧しそうなお宅に泊めてもらえることになった。
「今日は特別なお客さんだから、特別料理ですよー!」
てな感じでおかみさんがワザワザ買ってきたものは、バケツに山盛り入った理科の解剖実験直後のような内臓の山。
それを、素材の味を究極に活かし切る料理法「塩茹で」にしたものが私の前のさらにドサッと盛られた。
せっかくのもてなしを「これは食えません」などと言って断ることはできぬ。
オートリバースしてしまいそうなうごめく胃袋(私のね)を押さえつけ、冷や汗タラタラ、ひざガクガク、涙目になりながら何とか食べれば
「どう、おいしい?」
「はい、おいしいです」
ドサッ、再び山盛り・・・。
ゴミの話
日本では当たり前のように只で手に入り、身の周りにいくらでもあるが、他の国では手に入りづらい物。
ポケットティッシュなんか代表例かもしれない。
例えばインドなどで。
このコラムはどうでもいい紙に下書きしてからネット屋に行くのだけれど、この「どうでもいい紙」というのがなかなかないのだ。
日本では広告の裏、銀行とかで勝手にくれるメモ帳、職場・学校などで出るコピーの裏紙などチョチョイと書いてポイと捨てられる紙がいくらでもある。
が、インドにはない。
よって文具屋で雑記帳を買わねばならない。
例えば中国で。
スーパーでもらえるビニール袋。
荷物を濡らさぬよう個別でくるむのに多数必要なんだけど、中国ではこういう丈夫なビニール袋がなかなか手に入らないのだ。
もちろん商店で買い物すればビニール袋には入れてくれるんだけど、これがペラペラのヘナヘナで、枝付の果物(ブドウとか)など入れればアッという間に破れてしまう。
ある時砂糖を買って帰る途中、いつの間にか穴が開いてて宿に着く頃には半分くらい無くなっていた。
ロケット飛ばす前に丈夫な袋作れ!と言いたい。
以前は大きな町の大型スーパーならしっかりしたのが手に入ったのだが、今年ラサのスーパーに行ったら「環境保全どーたら」とかかれた紙袋を10円で買うシステムになっていた。
他の中国の街でもそうなっているのかもしれない。
多くの国で。
自転車のフレームに水筒として使う1.5Lのペットボトルをつけてある。
これは日本を出た時からずっと使い続けている日本製の物。
もちろんこちらにもペットボトルに入った水は売っているので新しいボトルはいくらでも手に入る。
しかし材質が薄くてすぐベコベコになってしまうし、中国では飲み水をもらおうとすると魔法瓶に入った熱水をくれるのでシュワシュワと縮んで1.2Lぐらいになってしまうのだ。
やっぱり日本製がイチバン!
だけど考えてみれば、私の例は特別であって普通の生活の中ではどうせ捨てちゃうんだからペットボトルなんて薄くても問題ない訳だ。
ビニル袋だって家に帰り着ける程度の丈夫さがあればいい訳だ。
日本ではなんと無駄な物に資源を費やしているのだろう・・・。
モーニングコール
インド、というと不潔・汚いのイメージ強く、実際街はゴミ・ウンコ・死体が散乱していて確かに汚いのだけど、私の見るところ一般のインド人はとても清潔である。
服は毎日こまめに洗うし、宗教と関係する沐浴の習慣はあるし、道端の共同水道ではパンツ一丁で泡まみれになって体を洗っている姿をよく見かける。
歯磨きもかなり熱心だ。
苦い粉をブラシにつけて磨いている。
また木の枝を口に突っ込んでいる人もいて、はじめは
「さすがインド人!木の枝まで食うのか?!」
と驚いたが、そうではなくてこれは歯磨き用枝なのだった。
私もやったことあるが、枝をガジガジ噛むと先がブラシのようにボサボサになり、それで歯をゴシゴシやる。
枝からは殺菌作用がある(らしい)苦い汁が出てまことに理にかなっているようだ。
また「舌磨き」の習慣もちゃんとある。
やったことある人は分かると思うが、あれは舌の奥の方までしっかりやろうとすると必ず「オエッ!」となるものだ。
だからインド人用の宿で水場に近い部屋に泊まったりすると朝早くから「オエッ!」「ウエッ!」「オエッ!」「オエッ!」と連発で響いてきて、心地よい目覚めができること請け合いなのだ。
白人旅行者のフシギ(5)
<その5.やたらカバンがデカイ>
体も大きいから100Lのザックを背負っても平気・・・
なのかもしれないが、ハブラシやシャツが5倍もあったりする訳なかろう。
何週間ものトレッキングに出かけるのでもないのに何をあんなにたくさんの荷物持っているんだろう??
ある時気になって見せてもらったことがある。
まずは軽いジャブ、といった感じでペーパーバック五冊出てきた。
フム、本の好きな奴なんだな、と油断したところへ強烈なボディーブローが来た。
靴が三足出てきた。
しかも一足はフォーマルな革靴で木のシューキーパーまで入っている。
「パーティーなんかに呼ばれたら必要だろ」
その後もワンツーなどのコンビネーションが確実に決まる。
家族・彼女の写真(額入)、キャンドルスタンド、CD数十枚・・・
そして。
全体重をのせたコークスクリューパンチがテンプルに突き刺さった。
オレは静かにマットに沈んだ。
「枕」だった。
「これじゃないと眠れないんだ」
薄らいでゆく意識の中でオレは何度も繰り返した。
「そんなんだったら家にいればいいのに・・・」
白人旅行者のフシギ(4)
<その4.ケチなのか金持ちなのか>
リキシャ・タクシーや土産物屋で、買い手市場を活かして1ルピー(1.5円)の単位まで鬼のように値切り倒す人がいる。
「おー、彼らも1円まで節約して細々と旅をしている倹約旅行者なのね」
と感心していると、同じ人が今度はツーリスト向けレストランで高くてマズいスパゲティーなんかをビールを飲みながら悠々と食っているのである。
ローカル向け食堂でカレー食えばその何分の一で済むのに・・
白人さん達は概してそういう薄汚い食堂で食うのを好まないようだ。
「大衆食堂でカレーを手掴みで食べるフランス人カップル」
なんてのをフィルムに収めることができれば、その年のピューリッツァー賞はほぼ手中にしたといえよう。
白人旅行者のフシギ(3)
<その3.日光浴が好き>
夏にリゾート地に行ってごらんなさい。
そこには「白人」はいない。
いるのは「赤人」である。
「何もそんなになるまで・・・」とア然としてしまう程まっかっかに日焼け、いや火傷を負ったシミソバカスだらけの赤人さん達がウロウロしている。
あのまま熱い風呂にでも入ったら飛び上がって天井を突き抜けそうである。
ある筋から聞いたところでは、夏休み明けにあおっちろい肌をしていると「プアホワイト」といって、バカンスにも行けない貧乏人として馬鹿にされるらしい。
真実だとしたらなんとも哀れな話である。
白人旅行者のフシギ(2)
<その2.彼らはまぶしい>
「キャー、レオ様ってステキ!輝いてるわ!」とか、ハゲばかりとかいう話ではない。
彼ら自身が日光をまぶしがっている、という意味である。
白人のサングラス着用率はかなり高い。
白色人種は色素が少なくどーのこーの、ということではあろうが、私などは幼き頃、
「サングラスをかけたる者、及び、左ハンドルの車に乗る者、これ即ちヤクザ」
という教育を受けてきたため、夏に欧米を訪れれば全国民総極道化してしまい怖くて外を歩けないだろう。
老若男女皆サングラスなので、前述の屋上レストランなどで家族揃ってサングラスをかけながらスパゲティー食ってる姿がなんとも奇妙に思えてしまう。
チベットでは雪目になってしまってヒリヒリして困ったが、そういう訳で私自身はサングラスはしないのだ。
同行のスイス人が「サングラスしないと紫外線が目に入って良くないんだゼイ」
とアドバイスしてくれてごもっともとは思ったが、それは次項とは大いに矛盾する。